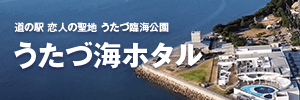本文
令和7年度からの風しんの追加的対策について
このページは、風しんの第5期定期接種対象者の方(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方)へのご案内です。
※令和7年4月1日付、事業終了に伴いホームページのタイトルを「風しんの追加的対策について」から変更しています。
風しんとは
風しんは、感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき(飛沫)を吸い込んで感染し、1人の感染者から5~7人にうつす感染力の強い感染症です。自覚症状がない場合もあり、電車や職場など人が集まる場所で、気づかないうちに多くの人に感染させるリスクがあります。大人が風しんに感染すると、子どもに比べ関節痛が強いことが多く、発熱や発疹の期間も長く重症化することがあります。
また、妊娠早期(20週以前)の方が風しんに感染すると、目・耳・心臓などに障害(先天性風しん症候群)がある赤ちゃんが生まれることがあります。
風しんは、ワクチンで予防できる感染症です。
【令和6年度末で終了】風しんの追加的対策について
令和6年度末まで、風しんの追加的対策として、これまで予防接種法に基づく定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて低い、1962(昭和37)年4月2日~1979(昭和54)年4月1日生まれの男性について、風しん抗体検査及び定期予防接種を実施してきました。
なお、妊娠を希望する女性や、風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者など同居者も香川県が実施する「風しん抗体検査事業」を利用することができます。対象者や実施期間、検査の受付など詳細については県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
風しんワクチンの接種費用助成のお知らせ
(麻しん・風しんの定期予防接種の接種期間延長)
国においては、麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に、接種ができない方がおられると見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。
国の方針にもとづき、次の対象者のうち、令和7年3月31日までに接種ができなかった方について、接種対象期間を2年延長します。
接種対象期間延長対象者
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、風しんの抗体が不十分であった方。
(令和7年4月1日以降に抗体検査を実施した方は対象外です。)
接種可能な期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間 ※診療時間内
自己負担金
宇多津町から送付される予診票を使用すれば無料。
使用するワクチンと回数
麻しん風しん混合ワクチンを1回接種。
接種方法
実施医療機関一覧表を同封しますので、接種を希望する医療機関に予約をしてください。
接種の際に持参するもの
対象となる方には、令和7年5月中に「風しん5期予防接種予診票(白茶色)」をお送りしますので、必ず持参してください。
※昨年度までのクーポン券(シールタイプ)は使用できません。
予診票を紛失した場合
予診票を紛失された方は、再発行しますので本人確認書類を持参のうえ、保健センターまでお越しください。ご本人の来所が難しい場合は、委任者と代理人の本人確認書類と委任状を持参してください。
県外で予防接種を受ける場合
接種前の手続きについて
必ず接種を受ける前に申請してください。定期予防接種をやむを得ない事情により香川県外の医療機関で接種する場合には、宇多津町が発行する「予防接種実施依頼書」を医療機関へ提出することで、予防接種を受けることができます。書類の発行には、申請書受付後、約1週間ほどかかりますので、余裕をもって申請してください。
接種費用は、一旦全額自己負担となり予防接種後に、宇多津町が定める金額の払い戻しを受けることができます。予防接種実施依頼書なしに接種した場合は、費用助成を受けることができませんのでご注意ください。
(参考)「予防接種実施依頼書」とは、万が一定期予防接種により引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合、宇多津町が救済措置を行うことを明確にしたものであり、県外で接種する場合は原則必要となります。
宇多津町予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/42KB]
※申込書は宇多津町保健センター窓口にも置いています。
送付先
〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町保健センター「予防接種担当」行
※封筒表面に「予防接種実施依頼書交付申請書在中」とご記入ください。
県外医療機関での接種時・接種後の手続きについて
接種時には必ず、予防接種実施依頼書と町から送付された予診票を医療機関に持参してください。接種後は、償還払いの申請が必要です。
還付申請時に必要な書類
- 定期予防接種料金還付請求書(「予防接種実施依頼書」とともにお送りします)
- 医療機関発行の領収書(原本)
- 予防接種予診票のコピー
- 振込先口座名義・口座番号記載ページの写し
(注)無料で接種した場合は還付請求できません。
(注)有料で接種した場合は、「定期予防接種料金還付請求書」に必要事項を記入し、他の書類とともに、接種後1ヶ月以内(ただし、3月接種分は4月10日まで)に還付請求してください。
(注)「定期予防接種実施依頼書」なしに、契約医療機関外で接種した場合は、還付請求による助成を受けることができませんのでご注意ください。
接種後の健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。給付の種類・内容は定期接種の種類によって異なります。高齢者の帯状疱疹ワクチンの定期接種は、「B類疾病の定期接種」として位置づけられています。
- 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームぺージ)(外部リンク)<外部リンク><外部リンク>