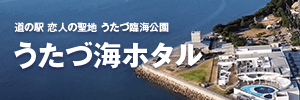本文
配偶者からの暴力(DV)等に関する相談
ひとりで悩まず、相談を。
配偶者や交際相手からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、人身取引、セクシュアルハラスメント等は決して許されない行為です。
宇多津町相談支援センターでは、配偶者からの暴力(DV)等に関する相談に応じています。年齢、性別を問わずご相談できます。お気軽にご相談ください。(相談は無料、秘密厳守)
宇多津町の相談窓口
宇多津町相談支援センター
電話番号:0877-49-8028
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
香川県の相談窓口
香川県子ども女性相談センター
電話番号:087-862-8861
その他相談窓口
| 相談先 | 電話番号等 | 相談できる内容 |
|---|---|---|
| 内閣府 DV相談ナビ ※近くの配偶者暴力相談支援センターにつながります。 | #8008 | 配偶者・交際相手からの暴力 |
| 内閣府 DV相談プラス ※24時間受付。外国語相談対応。 | 0120-279-889 SNS、メール相談可能 |
配偶者・交際相手からの暴力 |
| 内閣府 性暴力に関するSNS相談 Cure time(キュアタイム)<外部リンク> | SNS、メール相談可能 | 性犯罪・性暴力 |
| 内閣府 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター | #8891 | 性犯罪・性暴力、AV出演被害 |
| 警視庁 性犯罪被害者相談電話(全国共通) | #8103 | 性犯罪に係る被害や捜査 |
| 警視庁 匿名通報ダイヤル | 0120-924-839 | 性犯罪に係る被害や捜査、売春強要や人身取引 |
| 警視庁 警察相談専用電話 | #9110 | 犯罪被害に関する相談全般 |
| 法務省 女性の人権ホットライン(全国共通) | 0570-070-810 | 女性の人権侵害に関する相談 |
| 法務省 外国語人権相談ダイヤル(全国共通) | 0570-090911 | 外国人の権侵害に関する相談 |
| 法務省 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル(全国共通) | 0120-079714 | 法的トラブルに関する相談 |
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
DVとは配偶者(事実婚や元配偶者も含む)など親密な関係にある男女間でふるわれる暴力のことです。「暴力」には様々な形態があり、多くは複数の暴力が重なって起こっています。また、ある行為が複数の暴力の形態に該当する場合もあります。
| 身体的暴力 | 平手で打つ/げんごつで殴る/足でける/身体を傷つける可能性のある物で殴る/刃物などの凶器を体に突き付ける/首を絞める/腕をねじる/引きずり回す/髪を引っ張る/物を投げつける など |
|---|---|
| 精神的暴力 | 大声で怒鳴る/「誰のおかげで生活できるんだ」などと言う/無視して口をきかない/人の前でバカにしたり、命令する口調でものを言う/大切にしているものを壊す、捨てる/物を投げつけるふりをして脅かす など |
| 社会的暴力 |
実家や友人と付き合うのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックする/「外で働くな」と言ったり、仕事を辞めさせたりする/位置情報を監視される など |
| 経済的暴力 | 生活費を渡さない/お金を勝手に使う/家計をかえりみず浪費する、借金を重ねる など |
| 性的暴力 | 見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる/いやがっているのに性行為を強要する/中絶を強要する/避妊に協力しない など |
| 子どもを巻き込んだ暴力 | 「子どもに危害を加える」と言って脅す/子どもに自分を非難するようなことを言わせる など |
デートDVとは
DVとは配偶者(事実婚や元配偶者も含む)など親密な関係にある男女間でふるわれる暴力のことですが、その中でも、恋愛関係にある男女間での暴力を「デートDV」と言います。
DVのサイクル
多くの場合、DVには「緊張期」「爆発期」「ハネムーン期」のサイクル(周期)があり、何度も繰り返されると言われています。
ハネムーン期で加害者が優しくなるのは、被害者が離れていくのを防ぐためです。このとき被害者は暴力がなくなるかもしれないと期待を抱き、逃げるタイミングを失います。このサイクルが何度も繰り返されると、被害者は「離れることができない」「この関係の中でなんとかやっていきたい」と思うようになります、支配関係が強化されてしまいます。
心や身体への影響
DVは被害者の心や身体に深刻な傷を残してしまいます。暴力被害を受けると、常に危険を感じ緊張や恐怖心がつきまといます。加害者からの暴力や罵倒によって自尊心を失い、自己否定感を感じます。多くの場合、加害者と離れても精神的な影響は続きます。
子どもへの影響
DVは家庭内で起こることが多く、子どもにも深刻な影響を与える場合があります。子どもはDVを目の当たりにして、心に大きな傷を負ってしまします。「児童虐待の防止に関する法律」では、児童の目の前で家族に暴力をふるうことは児童への心理的虐待にあたるとされています。
暴力や緊張感のある夫婦関係の中で育つことによって、子どもは様々な行動や心身の症状を呈します。落ち着かない、暴力的になるなどのほか、不眠、頭痛、腹痛などを訴え、学習にも悪影響を生じます。「悪いから暴力を振るわれる」「思い通りにならない時は暴力を振るう」など、自分の育った家庭での人間関係のパターンを取り入れ、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることもあります。
まずは相談機関へ相談を
「自分さえ我慢すればいい」「自分が悪いから暴力を振るわれた」と考えていませんか?DVは被害者一人の力で容易に解決できる問題ではありません。まずは、DV相談機関に相談しましょう。
被害者が暴力を受けないためには、加害者のもとを離れるという選択肢もあります。このとき「どのようなタイミングで家を出るのか?」「家を出るときの持ち物は?」「家を出た後はどうするのか?」「子どもの学校はどうするのか?」などの現実的な問題が生じてきます。これらの問題を、事前に相談機関で一緒に整理しておくことは、被害者の安全のために必要なことです。ひとりで抱え込まないでまずは相談してください。秘密は守られます。